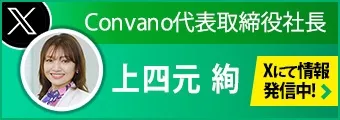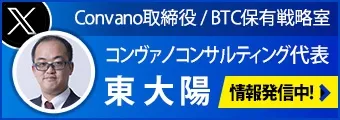FAQ
よくある質問
ビットコイン指標と
今後の関わりについて
-
BTCイールドとは?
-
BTCイールドとは、一株当たりのビットコイン保有量がどのように増減したかを表す指標です。
弊社では新株予約権の発行や社債等の各手段を通じて資金調達し、ビットコイン取得を進めています。
今後、資金調達による希薄化の影響(議決権保有割合の低下や1株あたり利益/純資産の低下)を上回るビットコイン保有による利益創出を目指していきます。
そのため、BTCイールドとは弊社にとってどの程度効率的にビットコイン取得が進められているかを測る重要な指標としています。
-
BTCゲインとはBTC円ゲインとは?
-
BTCゲインとは、希薄化の影響を除外し、財務戦略によってもたらされたビットコインの純増加を数値化した指標です。
対象期間開始時のビットコイン保有高に同期間のBTCイールドを掛けることで計算します。
一方、BTC円ゲインはBTCゲインの円換算額を表し、該当期間の最終日のビットコイン市場価格を乗じて算出します。
BTCイールドと合わせて計測することで、当社の資本配分効率およびビットコイン取得戦略の有益性をより理解できると考えています。
-
BTCイールドを算出する際の株式数の定義は?
-
BTCイールドを算出する際の株式数には、完全希薄化後発行済株式数を用います。
完全希薄化後発行済株式数は、以下のように定義されています。
完全希薄化後発行済株式数 =
既存の発行済株式総数 +
潜在株式数
潜在株式数 = 発行済みの新株予約権がすべて行使された場合の株式数
-
国内BTC保有量ランキングとは?
-
BITCOIN TREASURIES.NETのデータに基づいたものであり、BITCOIN TREASURIES.NETは、各企業の開示済み資料の情報に基づきランキングを作成しています。
本ランキングは、保有量に関する新たな情報開示から反映までに遅れが生じる可能性があります。
-
今後目標とする保有数量について
-
2025年度〜2026年度の2カ年を通じて段階的にビットコインを取得する「三層フェーズ構造」を採用します。
PhaseⅠ(2025年12月末基準)
2,000 BTC 取得
Phase Ⅱ(2026年8月末基準)
8,000BTC 取得
Phase Ⅲ(2027年3月末基準)
11,000 BTC 取得
Phase Ⅰ、Phase Ⅱ、Phase Ⅲの合計で想定取得総額は4,340億円程度(1BTC=1,990万円想定)です。
発行上限2,100万 BTCの0.1%、すなわち21,000 BTCという水準は、世界的に見てもコーポレート・トレジャリー用途としては上位30位圏に入り、国内に限れば群を抜く規模です。
これだけの保有量を確保することで、当社は単なる利用者やサービス提供者の枠を超え、基軸資産を自社で裏付ける「レイヤー0」プレイヤーとして、エコシステム全体のガバナンスと流動性に実質的影響力を持つことが可能になります。
※参照: 2025年8月4日 適時開示 「コンヴァノ21,000ビットコイン財務補完計画」策定のお知らせ
-
当社のビットコインに関する長期ビジョン
-
当社の財務基盤の強化及び円建て中核事業の成長に伴う購買力維持策、中期的なインフレ影響への緩衝措置を目的とした取り組みの一環として、資産の一部をビットコイン(BTC)で保全する、長期保有を前提としたビットコイン保有戦略を定めています。
近年の物価上昇・為替変動を踏まえ、企業経営におけるインフレ耐性及び通貨分散の重要性が一層高まっています。
当社は、資産の一部をビットコイン(BTC)で保全するビットコイン保有戦略を決議しましたが、その前提として、2025年6月27日の株主総会で定款目的に「Web3・デジタルアセット事業」を追加し、2025 年6月30日付「第三者割当による第 4 回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の引受契約の締結に関するお知らせ」でデジタルアセットへの投資を開示しています。
本戦略は、円建て中核事業の成長に伴う購買力維持策、中期的なインフレ影響への緩衝措置として位置付けるものであり、将来的に財務諸表上でBTC等の比率が相対的に高く見える可能性がありますが、これは「円で稼ぎ、円の購買力を守る」財務防衛機能であると位置づけています。
また、一部の上場企業ではビットコインを財務戦略資産として保有する動きが広がっており、長期的な資産保全の手段としての活用が進んでいます。
当社においても、事業成長に伴う資産運用の一環として、円建て資産のみならず、インフレヘッジ及び価値保存資産としてのビットコインを組み入れることで、財務健全性の向上を図ることを目的としています。
-
BTCの取得と保管方針
-
取得にあたっては、価格変動リスクを分散させるため時間分散・価格分散のストラテジーを採用します。
具体的には、下記を組み合わせるハイブリッド手法を採用します。
①Phase Ⅰでは次で均等購入を行うDollar-Cost Averaging
②相場急落局面での裁量バリュー投資
開示内容について
-
社債の発行について
-
当社は、社債発行戦略において市場環境に応じて、効率的かつ適切な条件が得られる通貨での社債発行が可能です。
発行判断にあたっては、市況、通貨の流動性、資金調達のタイミング、業務上の資金ニーズなど鑑みて、総合的に判断しています。
社債発行は主に、当社の投資方針に沿ってビットコインをインフレヘッジ及び価値保存資産として蓄積・保有することを目的としています。
今後も引き続き、各種法定通貨で資金を調達し、ビットコインの追加取得に充てていく方針です。
-
新株予約権の発行について
-
当社は普通株式の希薄化を極力回避することを資本政策の基本方針とし、現在CFOにより資金調達方法を検討中です。
具体的には、株価水準・流動性・需要動向を総合的に勘案した上で決定いたします。
実行に際しては、 下記のような社内方針を策定した上で、株主利益への影響を最小限にとどめる計画です。
①1回当たりの希薄化率を10%未満に抑制し、段階的に実施
②発行価格の決定時にはディスカウント率を一定以内に制限
③累計希薄化率が25%を超える場合は臨時株主総会を開催し、増資の必要性・相当性について株主の承認を得る